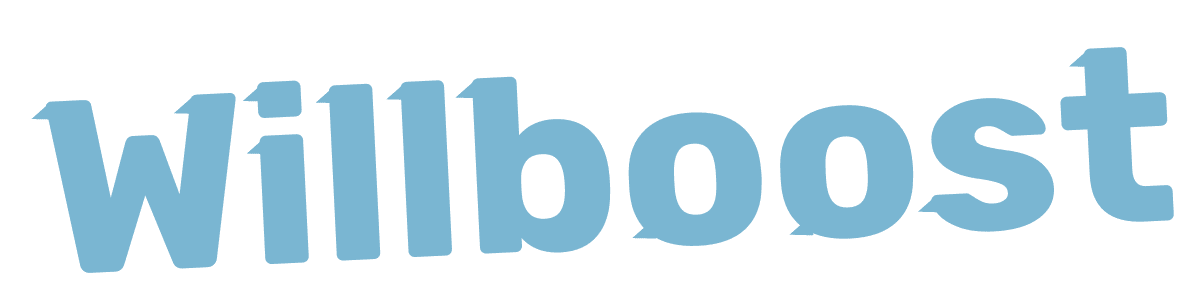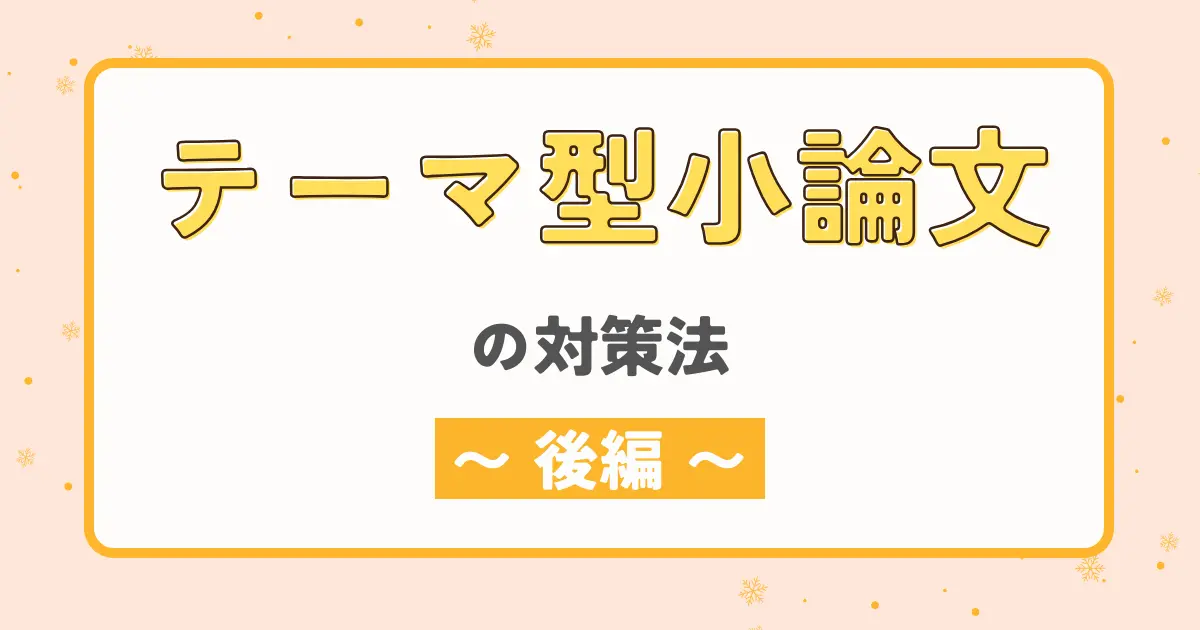前編では、テーマ型小論文の攻略の鍵をを中心に見ていきました。
後編では、「医学部頻出時事ネタや主張例」「時間配分や実践テクニック」などを中心に理解していきましょう。
2025年 医学部頻出時事ネタ一覧と主張例
2025年の医学部入試で出題が予想される時事テーマと、それぞれのテーマで展開できる主張例をご紹介します。
医療AI・デジタルヘルス
主要トピック:
- 診断支援AI、手術ロボット
- 電子カルテ、オンライン診療
- ウェアラブルデバイス、遠隔モニタリング
- 医療データの活用とプライバシー
主張例1:技術活用推進派
「AIは医師の診断精度向上と業務効率化に貢献するため、積極的に導入すべき。ただし、最終判断は必ず医師が行い、患者との関係性を重視した医療を維持することが重要。」
根拠パターン:
- 画像診断AIの精度向上データ
- 医師の働き方改革への寄与
- 地方医療への技術提供の可能性
主張例2:慎重導入派
「技術の恩恵は認めつつも、医療の人間性や医師の判断力低下を防ぐため、段階的かつ慎重な導入が必要。技術に依存しすぎない医療体制の構築が重要。」
根拠パターン:
- 誤診のリスクと責任の所在
- 患者とのコミュニケーション機会の減少
- 医師のスキル維持の重要性
高齢化社会と地域医療
主要トピック:
- 医師の地域偏在、医師不足
- 在宅医療、地域包括ケア
- 高齢者医療、認知症対策
- 医療費増大、持続可能性
主張例1:地域医療充実重視
「高齢化が進む地域社会では、病気の治療だけでなく、予防と生活支援を含めた包括的な医療が必要。医師は地域住民の健康の守護者として、より幅広い役割を担うべき。」
根拠パターン:
- 地域医療の現状と課題
- 予防医学の費用対効果
- 住民との信頼関係の重要性
主張例2:効率的医療提供重視
「限られた医療資源を最大限活用するため、ICTを活用した効率的な医療提供体制と、専門医の適切な配置が重要。集約化と分散化のバランスを取った医療体制の構築が必要。」
根拠パターン:
- 医療資源の現状と将来予測
- テレメディシンの可能性
- 医療の質と効率性の両立
感染症対策と公衆衛生
主要トピック:
- パンデミック対策、感染症の制御
- ワクチン政策、予防接種
- 国際的な医療協力
- 新興感染症への対応
主張例1:予防重視・国際協力派
「感染症対策では治療よりも予防が重要であり、国際的な協力体制と、日頃からの公衆衛生システムの強化が不可欠。医師は個人の治療者としてだけでなく、社会の健康守護者として行動すべき。」
根拠パターン:
- COVID-19から得た教訓
- ワクチンの有効性データ
- 国際協力の重要性
主張例2:バランス重視派
「感染症対策と経済活動・社会活動のバランスを重視し、科学的根拠に基づいた合理的な判断が重要。過度な制限は別の健康被害を生む可能性があるため、総合的な健康への視点が必要。」
根拠パターン:
- 外出制限による健康への影響
- 経済活動と健康の関係
- メンタルヘルスへの配慮
医療倫理・生命倫理
主要トピック:
- 終末期医療、尊厳死
- 臓器移植、再生医療
- 遺伝子診断・治療
- インフォームドコンセント
主張例1:患者自律性尊重派
「医療の最終目標は患者の幸福であり、そのためには患者の価値観と自己決定権を最大限尊重することが重要。医師は専門知識を提供する立場として、患者の意思決定を支援すべき。」
根拠パターン:
- 患者の価値観の多様性
- QOLの重要性
- 医師-患者関係の変化
主張例2:生命の尊厳重視派
「生命の尊厳を最優先とし、可能な限り生命を保護することが医師の使命。ただし、無意味な延命は避け、患者の苦痛軽減に最大限配慮した医療を提供すべき。」
根拠パターン:
- 医師の職業倫理
- 生命の価値の絶対性
- 苦痛緩和の重要性
医師働き方改革
主要トピック:
- 労働時間制限、医師の健康管理
- 医療の質と効率性
- 医師不足への対応
- チーム医療の推進
主張例1:働き方改革推進派
「医師の健康と働きやすさは、最終的に患者の利益につながる。適切な労働環境の下で働く医師こそが、質の高い医療を継続的に提供できる。制度改革と意識改革の両面から取り組むべき。」
根拠パターン:
- 過労による医療事故のリスク
- 医師のメンタルヘルス
- 持続可能な医療提供体制
主張例2:医療の質重視派
「医師の働き方改善は重要だが、それによって医療の質や患者へのアクセスが損なわれてはならない。効率化とチーム医療により、質を保ちながら働き方を改善する方法を模索すべき。」
根拠パターン:
- 医療の質への影響
- 患者の医療アクセス
- 医療チームの役割分担
活用のポイント
これらの主張例は参考として、自分なりの体験や価値観を加えて、オリジナルの主張を構築することが重要です。また、複数のテーマを組み合わせた論述も効果的です。
テーマ型特有の時間配分と実践テクニック
テーマ型小論文では、課題文を読む時間がない分、思考と構成に多くの時間を配分できます。しかし、それゆえに時間配分を間違えると大きな失敗につながります。
知識の整理から執筆までの時間管理
60分のテーマ型小論文の理想的時間配分
思考・整理フェーズ(15分)
- テーマ分析:3分
- 論点整理:5分
- 主張決定:4分
- 構成計画:3分
執筆フェーズ(40分)
- 導入執筆:8分
- 展開執筆:24分
- まとめ執筆:8分
見直しフェーズ(5分)
- 論理チェック:2分
- 文字数調整:2分
- 誤字脱字確認:1分
アイデア発想の具体的手順
効率的にアイデアを発想し、整理するための手順です。
- ステップ1:ブレインストーミング(3分)
テーマに関連するキーワードや概念を思いつく限り書き出す - ステップ2:関連性の整理(2分)
書き出したアイデアをグループ化し、関連性を見つける - ステップ3:論点の絞り込み(3分)
最も論じやすく、独自性のある論点を選択 - ステップ4:主張の決定(2分)
選んだ論点に対する自分の立場を明確化 - ステップ5:根拠の確認(3分)
主張を支える根拠や具体例があるかチェック - ステップ6:構成の設計(2分)
導入・展開・まとめの大まかな流れを決定
書き始めで迷わないための準備法
執筆開始時に迷いが生じると、大幅な時間ロスにつながります。
準備すべき要素
導入の第一文 問題提起の文章を事前に決めておく
主張の表現 「私は○○だと考える」の形式を明確に
展開の順序 根拠1→根拠2→反対意見への対応など
使用する具体例 どの体験や事例を使うかを決定
まとめの方向性 未来への提案か、行動への決意かを決定
文字数調整の実践的コツ
テーマ型では、書きながら文字数をコントロールする技術が重要です。
文字数が不足している場合
具体例の詳細化 事例をより詳しく説明する
根拠の追加 別の観点からの根拠を加える
展開の深化 「なぜなら」を使ってさらに深く説明
未来展望の追加 まとめ部分で将来への言及を加える
文字数が超過しそうな場合
冗長表現の削除 「~と思う」「~と考える」の重複を避ける
具体例の簡潔化 事例の説明を要点のみに絞る
重複内容の削除 同じことを別の言葉で説明している部分を削除
優先順位の明確化 最も重要な論点に絞って論述
よくある失敗パターンと回避法
テーマ型小論文で多くの受験生が陥りがちな失敗パターンと、その対策法をお伝えします。
テーマからの逸脱を防ぐ方法
失敗パターン
「AIと医療」というテーマで、AIの一般的な技術論ばかり書いて、医療との関連が薄くなってしまう。
回避法
キーワードを常に意識 テーマに含まれる全てのキーワードに必ず言及する
段落ごとの確認 各段落でテーマとの関連性をチェックする
結論での振り返り 最後にテーマに対する答えになっているか確認
具体的テクニック
- テーマを問いの形に変換(「AIは医療をどう変えるか?」)
- 各段落の冒頭でテーマに関連する言葉を使う
- 「医療におけるAI」「AIを活用した医療」など、両要素を含む表現を意識的に使用
感情的になりすぎる書き方の修正
失敗パターン
「患者さんがかわいそう」「絶対に許せない」など、感情的な表現が多くなり、論理性が失われる。
回避法
客観的視点の維持 感情よりも事実と論理を重視
根拠の明示 感情的判断ではなく、合理的な理由を示す
冷静な表現の使用 「問題である」「改善が必要」など、落ち着いた表現を選ぶ
修正例
- 感情的:「患者さんがとてもかわいそうだと思います」
- 論理的:「患者の不利益が生じており、改善が急務である」
知識不足をカバーする書き方
失敗パターン
専門知識がないことで内容が薄くなったり、間違った情報を書いてしまう。
回避法
一般論からのアプローチ 専門的でなくても、一般的に理解できる範囲で論述
体験談の活用 個人的経験を根拠として効果的に使用
論理的思考の重視 知識よりも考え方の筋道を明確に示す
安全な表現の使用 「~と考えられる」「~の可能性がある」など、断定を避ける
カバーテクニック
- 「専門的な詳細は分からないが、基本的な考え方として…」
- 「一般的に言われていることとして…」
- 「素人目線から見た場合…」
ありきたりな内容を避ける工夫
失敗パターン
多くの受験生が書きそうな、予想可能で独創性のない内容になってしまう。
回避法
個人的視点の導入 自分ならではの体験や価値観を盛り込む
意外な角度からのアプローチ 一般的でない視点から問題を捉える
具体的な提案 抽象的でなく、実現可能な具体案を提示
複数要素の組み合わせ 単一の観点でなく、複合的な視点で論述
独創性を高める具体的方法
逆の視点から考える 「AI導入のメリット」→「AI導入で失われるもの」
異分野との関連付け 医療×教育、医療×環境など
時間軸の工夫 10年後、50年後の視点から現在を考える
当事者の視点 患者、医師、看護師など、特定の立場からの論述
まとめ
テーマ型小論文完全攻略法について、包括的に学んできました。最後に、重要なポイントを整理しておきましょう。
テーマ型攻略の5つの鍵
1. テーマの深読み 表面的な理解ではなく、出題意図や背景にある問題意識を読み取る
2. 戦略的な論点設定 広いテーマを適切に絞り込み、自分らしい視点で論じる
3. 多角的な根拠構築 体験・知識・時事問題を組み合わせた説得力のある論証
4. 計画的な時間管理 思考→構成→執筆→見直しの各段階での効率的な時間配分
5. 失敗パターンの回避 よくある間違いを事前に知り、対策を講じる
継続的な力向上のために
テーマ型小論文の実力向上には、継続的な取り組みが欠かせません:
日常的な練習
- 毎日1つのニュースについて自分なりの見解をまとめる
- 様々なテーマで5行まとめ訓練を継続
- 時事問題への関心を持ち続ける
知識の蓄積
- 医療・社会・科学技術分野の基礎知識を継続学習
- 具体例として使える体験や事例を収集
- 多角的な視点を養うための読書
実戦練習
- 実際の過去問でのタイムトライアル
- 添削を受けて客観的な評価を得る
- 他の受験生との議論で視野を広げる
最後に
テーマ型小論文は、難易度の高い形式です。しかし、だからこそ、しっかりと対策することで他の受験生との大きな差をつけることができます。
重要なのは、技術と思考力の両方を向上させることです。書き方のテクニックを身につけるだけでなく、物事を深く考え、自分なりの見解を形成する力を養ってください。
また、医学部志望者としての意識を常に持ち続けることも大切です。将来医師として社会に貢献したいという志を、小論文を通じて伝えてください。
準備は大変ですが、その過程で身につける思考力や表現力は、入試だけでなく、将来医師として働く上でも必ず役立ちます!