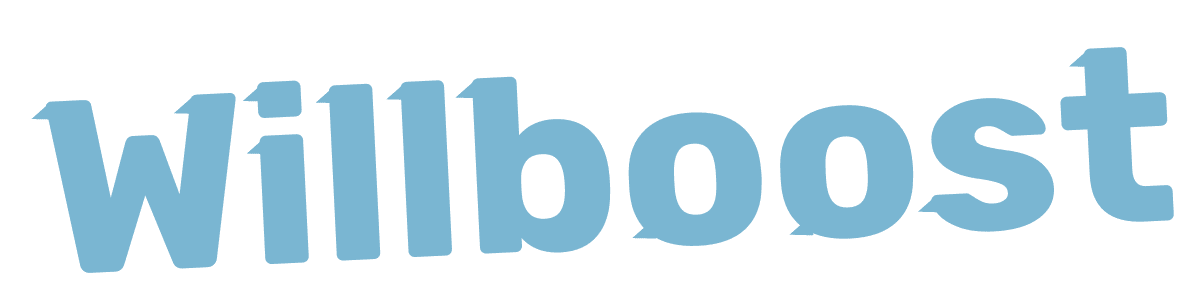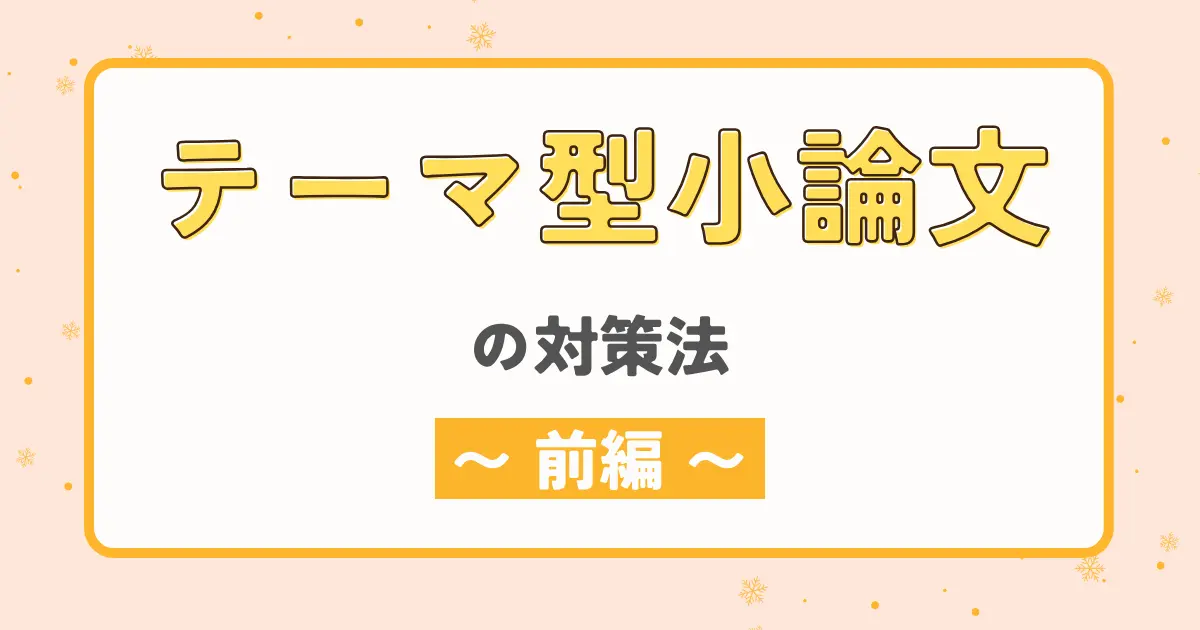このコンテンツでは、最も自由度が高く、同時に最も難易度の高い「テーマ型小論文」の攻略法をお伝えします。
- 「AIと医療の未来について論じなさい」
- 「理想の医師像について述べなさい」
- 「医療格差の問題と解決策を提案しなさい」
このような問題を見ると、「何から書き始めればいいか分からない」「知識が足りるか不安」「ありきたりな内容になってしまいそう」と感じる人も多いでしょう。
テーマ型小論文は、課題文という「手がかり」がない分、受験生の真の実力が問われる形式です。しかし、適切な対策法を身につければ、むしろ自分の個性や考えを最も効果的にアピールできる絶好の機会になります。

このコンテンツでは、テーマの読み解き方から時事ネタの活用法、さらには2025年入試で頻出が予想される具体的なテーマまで、テーマ型小論文で高得点を獲得するための全てのテクニックをお伝えします。
テーマ型は「自由に書ける」と思われがちですが、実は最も戦略的なアプローチが必要な形式なんです。この記事で、その戦略をしっかりと身につけていきましょう。
テーマ型小論文の特徴と対策の基本方針
テーマ型の独特な難しさ
テーマ型小論文は、他の出題形式とは根本的に異なる特徴を持っています。
課題文型との最大の違いは、手がかりとなる資料が一切提供されないことです。課題文型では、筆者の意見や具体的なデータが参考になりますが、テーマ型では全てを自分で考えなければなりません。
読解型との違いは、正解が存在しないことです。読解型では課題文に答えがありますが、テーマ型では自分なりの「答え」を創造する必要があります。
図表型との違いは、客観的なデータがないことです。数値で示せる根拠がない分、より主観的で説得力のある論証が求められます。
テーマ型で求められる3つの能力
テーマ型小論文では、以下の3つの能力が特に重要になります。
1. 問題発見力
与えられたテーマから、論じるべき核心的な問題を見つけ出す力。「理想の医師像」というテーマから「現代医療が抱える課題」を発見できるかどうか。
2. 知識活用力
断片的な知識を組み合わせて、説得力のある論証を構築する力。医療、社会、倫理など様々な分野の知識を統合する能力。
3. 独創的思考力
ありきたりではない、自分らしい視点や提案を示す力。多くの受験生が書きそうな内容とは一線を画す独自性。
対策の基本方針:「準備」と「柔軟性」の両立
テーマ型対策の基本方針は、十分な準備と本番での柔軟性の両立です。
準備の側面
- 頻出テーマの研究と自分なりの見解の形成
- 時事問題の継続的な学習
- 具体例や根拠となる知識の蓄積
- 基本的な論述パターンの習得
柔軟性の側面
- 予想外のテーマへの適応力
- 知識を組み合わせる創造力
- その場での論点設定能力
- 時間内での構成調整力
この両方をバランス良く身につけることが、テーマ型攻略の鍵となります。
評価のポイント:何が高く評価されるか
採点者がテーマ型小論文で重視するポイントを理解しておきましょう。
内容面
- テーマの本質を捉えているか
- 独自の視点や深い洞察があるか
- 具体的で説得力のある根拠があるか
- 医学部志望者らしい問題意識があるか
構成面
- 論理的で分かりやすい構成か
- 一貫した主張が展開されているか
- 適切な文字数配分ができているか
表現面
- 正確で分かりやすい文章か
- 適切な語彙が使われているか
- 読み手を意識した表現ができているか
これらのポイントを意識することで、より高い評価を得られる小論文が書けるようになります。
テーマの読み解きと論点設定のテクニック
テーマ型小論文で最初に直面する課題は、「与えられたテーマをどう解釈するか」です。ここでの判断が、その後の論述の方向性を決定づけます。
テーマの「真の意図」を見抜く方法
出題者は単純にテーマを提示しているように見えて、実は特定の能力や視点を見たいという意図を持っています。
「理想の医師像について述べなさい」の真の意図例
- 表面的には:医師に必要な資質を問う
- 深層的には:現代医療の課題を理解しているか、医師という職業への理解度、社会的視野の広さ
意図を読み解くコツ
- 時代背景を考える:なぜ今このテーマが出題されるのか
- 医学部の特性を考える:なぜ医学部志望者にこの問題を問うのか
- 社会的な関心を考える:現在社会で議論されている関連問題は何か
広すぎるテーマを適切に絞り込む技術
テーマ型では、しばしば非常に広範囲なテーマが提示されます。そのまま論じると散漫になってしまうため、適切な絞り込みが必要です。
絞り込みの手順
1. テーマの分解
「医療とAI」→「診断AI」「治療AI」「医療事務AI」「研究AI」など
2. 観点の設定
「効果・効率性」「安全性」「倫理性」「経済性」「人間性」など
3. 焦点の決定
自分が最も論じやすく、かつ独自性を発揮できる領域を選択
4. 論点の明確化
「診断AIは医師の役割をどう変えるか」など、具体的な問いを設定
論点を多角的に検討する思考法
優れた小論文を書くためには、一つの観点だけでなく、多角的な検討が必要です。
多角的検討の観点例
時間軸での検討
- 過去:従来はどうだったか
- 現在:現在の状況は
- 未来:将来はどうなるべきか
立場別での検討
- 患者の立場
- 医師の立場
- 社会の立場
- 制度・政策の立場
賛否両論での検討
- メリット・デメリット
- 推進派・慎重派
- 理想論・現実論
「問い」を自分で設定する重要性
テーマ型で最も重要なスキルの一つが、自分で適切な「問い」を設定する能力です。
良い問いの条件
- 答えがあまりにも自明でない
- 複数の視点から論じることができる
- 医学部志望者らしい専門性がある
- 現代的な意義がある
問いの設定例
テーマ:「医師に求められる資質」
- 浅い問い:医師にはどんな能力が必要か
- 深い問い:AI時代において医師にしかできない価値とは何か
テーマ:「地域医療の課題」
- 浅い問い:地域医療にはどんな問題があるか
- 深い問い:地域医療の持続可能性を高めるために医師はどう変わるべきか
深い問いを設定することで、より説得力があり、独自性のある小論文が書けるようになります。
時事ネタから自分の主張を考えるテクニック
テーマ型小論文では、時事問題への理解と自分なりの見解が重要な要素となります。しかし、単にニュースを知っているだけでは不十分です。時事ネタを自分の主張に有効活用するテクニックを身につけましょう。
ニュースの背景にある本質的問題の発見
表面的なニュースの奥にある、より深層的な問題を見つけることが重要です。
発見のプロセス
1. 事実の整理 何が起きているのかを正確に把握
2. 原因の分析 なぜそれが起きているのかを考察
3. 影響の予測 それが将来どんな影響をもたらすかを想像
4. 本質の抽出 その背景にある根本的な問題は何かを考える
具体例:「医師の働き方改革」のニュース
- 事実:医師の労働時間上限が設定された
- 原因:過労死問題、医師の健康管理、医療安全の観点
- 影響:医療の質への影響、医師不足の深刻化の可能性
- 本質:医療の質と医師の働きやすさの両立という根本的課題
この「本質」こそが、小論文で論じるべき核心的な問題となります。
複数の立場・視点からの分析方法
一つの時事問題を、異なる立場から分析することで、より深い理解と独自の視点を獲得できます。
立場別分析の例:「オンライン診療の拡大」
患者の立場
- メリット:通院負担の軽減、感染リスクの回避
- デメリット:診断の精度への不安、デジタル格差
医師の立場
- メリット:効率的な診療、地方への医療提供
- デメリット:診断の制約、患者との関係性の変化
医療機関の立場
- メリット:運営コストの削減、患者数の増加
- デメリット:システム導入費用、医療事故のリスク
社会の立場
- メリット:医療アクセスの向上、医療費の削減
- デメリット:医療格差の拡大、雇用への影響
このような多角的分析により、自分なりのバランスの取れた主張を構築できます。
自分の体験・価値観との関連付け
時事問題を単に外部の情報として捉えるのではなく、自分の体験や価値観と関連付けることで、説得力のある論述が可能になります。
関連付けの方法
- 直接的な体験との関連 「祖父のオンライン診療を見て感じた…」
- 間接的な体験との関連 「地元の病院の変化を通じて…」
- 将来の目標との関連 「将来医師として働く立場から考えると…」
- 価値観との関連 「私が重視する『患者に寄り添う医療』という観点から…」
医学部らしい視点の盛り込み方
時事問題を論じる際には、医学部志望者らしい専門的視点を盛り込むことで、他の受験生との差別化を図れます。
医学部らしい視点の例
- 医学的視点 「この技術が診断精度に与える影響は…」 「患者の予後改善の観点から…」
- 倫理的視点 「医師の職業倫理の観点から…」 「患者の自己決定権を尊重するためには…」
- 公衆衛生的視点 「社会全体の健康水準向上のためには…」 「予防医学の重要性から考えると…」
- 医療政策的視点 「持続可能な医療制度構築のためには…」 「医療資源の効率的配分という視点から…」
これらの視点を織り込むことで、医学部志望者としての適性をアピールできます。
説得力のある根拠の発見と活用法
テーマ型小論文では、自分で根拠を見つけ出し、効果的に活用する能力が重要です。限られた知識の中から説得力のある根拠を構築するテクニックを学びましょう。
体験談を普遍化する技術
個人的な体験を、多くの人に当てはまる普遍的な教訓に昇華させることで、強力な根拠として活用できます。
普遍化のプロセス
1. 体験の具体的描写 何が起きたのかを具体的に述べる
2. そこから得た気づき その体験から何を学んだかを説明
3. 一般化・普遍化 それが多くの人にも当てはまることを示す
4. 主張との関連付け その教訓が自分の主張をどう支持するかを説明
具体例:
「私が骨折で入院した際、看護師の些細な声かけが心の支えになった体験から、医療における人間的な関わりの重要性を実感した。この経験は、技術が進歩しても、患者の不安に寄り添う人間性こそが医療の本質であることを教えてくれた。」
統計データの効果的な使い方
正確な数値を覚えていなくても、大まかな傾向や比較を示すことで説得力を高められます。
データ活用のコツ
具体的な数値よりも傾向を重視 「約7割の患者が…」「2倍以上の差が…」
比較を明確に 「他国と比べて」「従来と比較して」「都市部と地方では」
出典を明確に 「厚生労働省の調査によると」「WHO報告では」
解釈を加える 数値だけでなく、その意味や背景も説明
注意点: 不正確な数値を使うよりも、「多くの」「大部分の」といった表現の方が安全です。
具体例の選び方と示し方
説得力のある具体例を選び、効果的に提示するテクニックです。
良い具体例の条件
- 多くの人が知っている、または理解しやすい
- 主張を明確に支持している
- 適度に具体的で、詳細すぎない
- 現代的で関連性が高い
具体例の示し方
導入の工夫 「例えば」「実際に」「具体的には」
適切な詳細レベル 必要以上に細かく説明せず、要点を明確に
主張との関連明示 「この例が示すように」「つまり」で主張につなげる
「なぜ」を3回繰り返す深掘り法
表面的な議論を避け、問題の本質に迫るための思考法です。
深掘りの例:「医師不足の問題」
1回目のなぜ:なぜ医師不足が問題なのか?
→ 患者が適切な医療を受けられないから
2回目のなぜ:なぜ適切な医療を受けられないと問題なのか?
→ 病気の早期発見・治療ができず、重篤化するリスクがあるから
3回目のなぜ:なぜそれが社会的に問題なのか?
→ 個人の健康が損なわれることで、社会全体の活力が低下し、医療費も増大するから
この深掘りにより、**「医師不足は個人の問題を超えた社会構造的課題」**という本質的な視点に到達できます。
深掘り法の活用場面
- 問題の本質を見極めたい時
- ありきたりな議論を避けたい時
- より深い洞察を示したい時
- 根本的な解決策を考えたい時
前編のまとめ
テーマ型小論文攻略の鍵について、一旦、重要なポイントを整理しておきましょう。
テーマ型攻略の5つの鍵
1. テーマの深読み 表面的な理解ではなく、出題意図や背景にある問題意識を読み取る
2. 戦略的な論点設定 広いテーマを適切に絞り込み、自分らしい視点で論じる
3. 多角的な根拠構築 体験・知識・時事問題を組み合わせた説得力のある論証
4. 計画的な時間管理 思考→構成→執筆→見直しの各段階での効率的な時間配分
5. 失敗パターンの回避 よくある間違いを事前に知り、対策を講じる



このコンテンツは一旦ここまでです。
次は、後編では「医学部頻出時事ネタや主張例」「時間配分や実践テクニック」などを見ていきましょう。