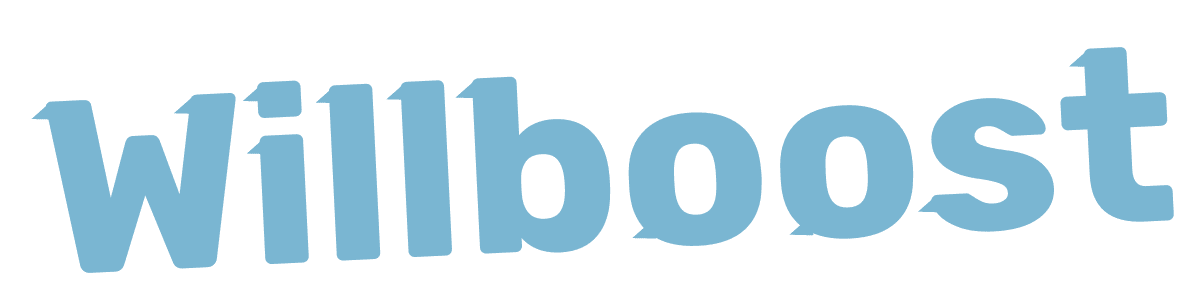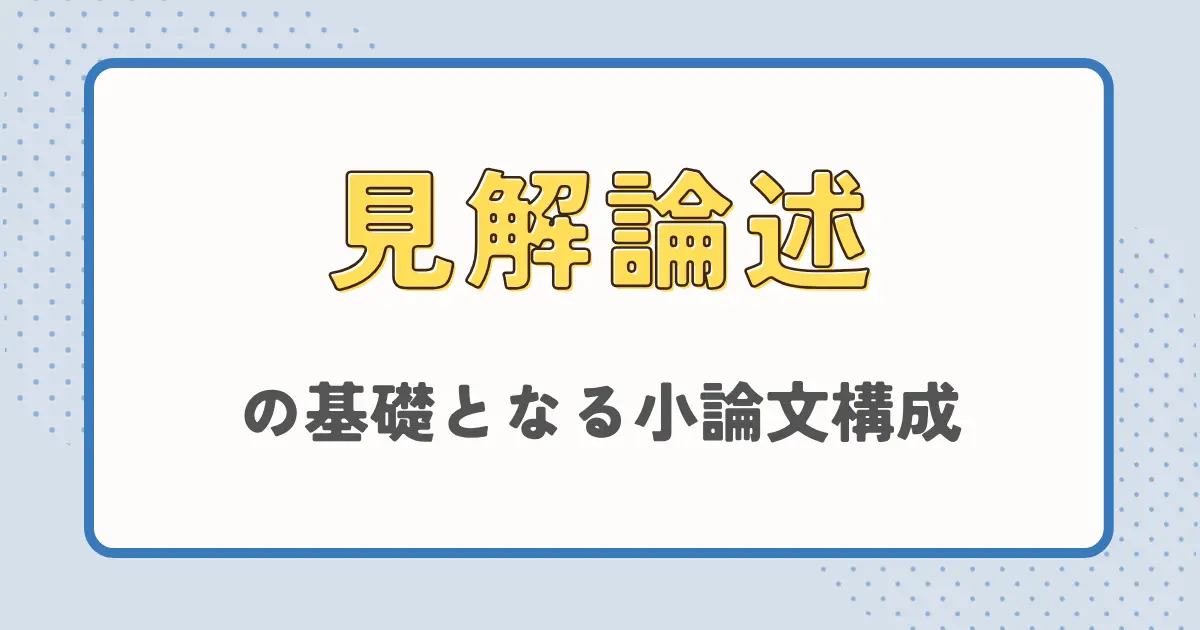前回のコンテンツで、小論文の出題形式や設問形式について学んでいただきました。「型」を理解することの重要性は理解できたでしょうか?
今回は、その中でも特に重要な「見解論述問題」の具体的な書き方について詳しく解説していきます。
「自分の考えを述べなさい」という設問を見ると、多くの人が「何を書けばいいか分からない」「どこから書き始めればいいの?」と戸惑ってしまいます。
でも実は、見解論述にも明確な「構成の型」があるんです。この型をマスターすれば、どんなテーマでも論理的で説得力のある小論文が書けるようになります。
「思ったことを自由に書く」のではなく、「型に沿って論理的に組み立てる」
これが、高得点を獲得するための秘訣です。

このコンテンツでは、見解論述の基本構成である「導入→展開→まとめ」の具体的な書き方と、日常でできる実践的な訓練方法をお伝えします。
1. 意見論述の基礎となる小論文構成の理解
見解論述問題で高得点を取るために、まず理解しておきたいのは「小論文の基本構成」です。
小論文は、決して思いつくままに書く文章ではありません。読み手にとって分かりやすく、説得力のある論理展開をするための、確立された構成があります。
基本構成は以下の3部構成です。
- 導入(15-20%):問題提起・テーマ提示・自分の主張
- 展開・論拠(60-70%):主張の理由・根拠・具体例
- まとめ(10-15%):主張の再確認・未来への提案
この構成は、論理的思考の自然な流れに沿っています。まず「何について論じるのか」を明確にし、次に「なぜそう考えるのか」を詳しく説明し、最後に「だからどうすべきか」を示す。
読み手にとって非常に理解しやすい構成なんです。
600-700字の小論文では、この比率を意識することで、バランスの取れた文章が書けるようになります:
- 導入:100-150字程度
- 展開・論拠:350-500字程度
- まとめ:50-100字程度
「でも、毎回文字数を数えながら書くのは大変…」と思うかもしれませんね。
安心してください。練習を重ねることで、この感覚は自然と身につきます。最初は意識的に構成を考え、徐々に無意識でもバランス良く書けるようになっていきます。
なぜこの構成が効果的なのか
この3部構成が効果的な理由は、人間の理解プロセスに合致しているからです。
- 人は何かを理解する時、まず「何の話なのか」を知りたがります。
- 次に「なぜそう言えるのか」の説明を求めます。
- 最後に「結局どういうことなのか」の確認をしたがります。
小論文の基本構成は、この自然な理解プロセスに沿っているため、読み手にとって非常に分かりやすい文章になるのです。
また、この構成は採点者にとっても評価しやすい形式です。論理的思考力、表現力、問題意識などを段階的に確認できるため、適切な評価が可能になります。
2. 導入:問題提起から主張まで
導入部分は、小論文全体の方向性を決める重要な部分です。ここで読み手の関心を引きつけ、自分が何について論じるのかを明確に示します。
導入の3つの要素
導入部分には、以下の3つの要素を盛り込みます:
- 問題提起・テーマ提示
- 背景や現状の説明
- 自分の主張(立場の明示)
問題提起・テーマ提示の技術
効果的な問題提起の方法をいくつか紹介します。
- 疑問文から始める 「AI技術の発達により、医師の役割はどのように変化するのだろうか。」
- 現状の課題を示す 「日本の地方では深刻な医師不足が続いており、適切な医療を受けられない住民が増加している。」
- 対立する意見を提示する 「医療AIの導入について、効率性を重視する声がある一方で、人間味のある医療を求める声も根強い。」
どの方法を使う場合も、自分が論じるテーマの範囲を明確にすることが大切です。テーマが曖昧だと、論述も散漫になってしまいます。
立場の明示が構成を安定させる
導入部分で最も重要なのは、自分の立場を明確に示すことです。
「私は○○だと考える」「○○すべきである」といった形で、最初に自分の結論を示してしまうのです。
「結論を最初に言ってしまったら、読む意味がないのでは?」と思うかもしれません。でも、小論文では「結論ありき」で構いません。むしろ、最初に結論を示すことで、その後の論述がブレにくくなるのです。
立場を明示する表現例
- 私は○○だと考える
- ○○すべきである
- ○○が最も重要だと思う
- ○○という立場を取りたい
この明確な立場表明があることで、展開部分では「なぜそう考えるのか」を集中して説明できるようになります。
導入部分の実例
テーマ:「理想の医師像について」
例1:疑問文からのアプローチ
「将来の医師には何が最も求められるのだろうか。医療技術の進歩により診断や治療の選択肢が増える中で、患者と向き合う医師の役割も変化している。私は、高度な専門知識以上に、患者の心に寄り添うコミュニケーション能力こそが、理想の医師に最も重要な資質だと考える。」
例2:現状課題からのアプローチ
「現代の医療現場では、医師の専門性が高度化する一方で、患者との意思疎通の問題が深刻化している。インフォームドコンセントの重要性が叫ばれる中、私は理想の医師像として、専門知識と人間性を兼ね備えた『対話する医師』を挙げたい。」
どちらの例も、問題提起→背景説明→立場表明の流れになっていることが分かります。
3. 展開・論拠:説得力ある論証の組み立て
展開部分は小論文の核心部分で、全体の60-70%を占めます。ここで自分の主張がなぜ正しいのかを、具体的な根拠とともに説明します。
展開部分の基本原則
展開部分で最も重要なのは、複数の段落に分けて、論点ごとに整理することです。
一つの段落に複数の論点を詰め込むと、読み手にとって分かりにくくなります。一つの段落では一つの論点を、丁寧に説明するのが基本です。
典型的な展開パターン(3段落構成)
- 第1段落:主要な根拠①
- 第2段落:主要な根拠②
- 第3段落:反対意見への反駁
説得力のある根拠の種類
根拠として使える材料は多岐にわたります:
1. 自分の体験・経験
最も説得力があるのは、自分自身の体験です。ただし、個人的すぎる内容は避け、一般化できる教訓を含むものを選びましょう。
例:「私が祖父の介護を手伝った経験では、医師の些細な声かけが患者の心理状態に大きく影響することを実感した。」
2. 身近な事象・社会現象
日常生活で観察できる現象や、広く知られている社会問題も有効な根拠になります。
例:「近年、医療現場での患者とのトラブルが増加しており、その多くがコミュニケーション不足に起因している。」
3. ニュース・報道
時事問題や最新の研究結果なども、根拠として活用できます。ただし、正確な情報であることが前提です。
例:「厚生労働省の調査によると、患者の満足度は医師の技術力よりも対応の丁寧さと強く相関している。」
4. 統計データ・調査結果
数値で示せる根拠は、客観性があり説得力が高くなります。
例:「医療事故の7割は、技術的ミスではなくコミュニケーションエラーが原因とされている。」
根拠の効果的な提示方法
根拠を提示する際は、以下の順序で説明すると効果的です:
- 根拠の提示:「例えば」「実際に」などで具体例を示す
- 詳細説明:その根拠の背景や詳細を説明
- 解釈・分析:その根拠が自分の主張をどう支持するかを説明
- 主張との関連付け:「このことから」「つまり」で主張につなげる
反対意見への対応で論述を深める
高度な小論文では、反対意見を想定し、それに対する反駁を加えることで論述に深みを与えます。
反駁の基本パターン:
1. 反対意見の紹介 「確かに、○○という意見もある」 「○○と考える人もいるだろう」
2. その意見の部分的認知 「その指摘には一理ある」 「この点については理解できる」
3. しかしの転換 「しかし」「だが」「とはいえ」
4. 反駁の根拠 なぜその反対意見が不十分なのかを説明
5. 再主張 改めて自分の立場を強化
展開部分の実例
先ほどの「理想の医師像」の続きを書いてみましょう。
「まず、患者の不安を和らげるためには、高度なコミュニケーション技術が不可欠である。私が祖父の通院に付き添った際、ある医師は難しい医学用語を一切使わず、図を描きながら病状を説明してくれた。この丁寧な説明により、祖父の不安は大幅に軽減され、治療に対する意欲も向上した。厚生労働省の調査でも、患者満足度は医師の説明の分かりやすさと最も強く相関していることが示されている。
また、医療技術が高度化する現代においても、最終的な治療方針の決定には患者の価値観や生活背景の理解が重要である。AIによる診断支援が進歩しても、患者一人ひとりの人生観に寄り添った医療を提供するには、人間同士の深いコミュニケーションが欠かせない。
確かに、専門知識の習得も医師には重要である。しかし、知識は継続的な学習によって補完できるが、患者との信頼関係を築くコミュニケーション能力は、医師としての根本的な資質として、早期から養う必要がある。」
この例では、体験談→統計→社会情勢→反駁という多角的な根拠を用いて、主張を支えています。
4. 結論(まとめ):効果的な結論の書き方
まとめ部分は、小論文全体を締めくくる重要な部分です。ここで読み手に強い印象を残し、自分の主張を確実に伝えます。
まとめ部分の3つの要素
効果的なまとめには、以下の要素を含めます:
- 主張の再確認
- 未来への提案・展望
- 自分の今後の行動(可能であれば)
主張の再確認のポイント
まとめでは、導入で示した主張をもう一度確認します。ただし、全く同じ表現を繰り返すのではなく、展開部分での論証を踏まえた、より説得力のある形で再提示します。
再確認の表現例
- 以上のことから、○○が重要であることは明らかである
- これらの理由により、私は○○すべきだと確信する
- このように、○○こそが最も大切だと考える
未来への提案で論文を発展させる
単に主張を繰り返すだけでなく、未来への提案や展望を加えることで、より建設的で前向きなまとめにできます。
提案の種類
- 具体的な解決策 「医学部教育において、コミュニケーション技術の訓練を必修化すべきである」
- 望ましい方向性 「技術と人間性のバランスを取った医療の実現が期待される」
- 社会全体への呼びかけ 「患者も医師との対話に積極的に参加する姿勢が求められる」
個人的な決意で説得力を高める
可能であれば、自分自身の今後の行動や決意を示すことで、より説得力のあるまとめにできます。
決意表明の例:
- 私も将来医師として、○○を心がけたい
- この問題解決のために、○○に取り組んでいきたい
- ○○の実現に向けて努力していく所存である
結論での注意点
まとめ部分では、新たな主張を持ち込まないことが重要です。これまでの論証で扱わなかった新しい論点を突然提示すると、論理的一貫性が損なわれます。
あくまで「これまでのまとめ」に徹し、既に論証した内容の範囲内で結論を導きましょう。
まとめ部分の実例
先ほどの「理想の医師像」の結論部分
「以上のことから、理想の医師には高度な専門知識以上に、患者の心に寄り添うコミュニケーション能力が最も重要であると考える。医療技術がさらに進歩する将来においても、患者との信頼関係を築く力こそが、医師という職業の本質であり続けるだろう。私も将来医師として、常に患者の立場に立って考え、心から信頼される医療者になりたい。」
この例では、主張の再確認→未来展望→個人的決意という流れで、印象的に論文を締めくくっています。
5. 小論文の構成理解を手助けする訓練
理論を理解したら、実際に練習してみることが大切です。しかし、いきなり600-700字の小論文を書くのはハードルが高いかもしれません。
そこで、日常的にできる効果的な訓練方法をご紹介します。
ニュースを読んで5行まとめ訓練
この訓練は、小論文の構成要素を凝縮した形で練習できる優れた方法です。一つのニュース記事を読んで、以下の5つの要素を1行ずつでまとめます:
- 1行目:記事の主張(何が問題とされているか)
- 2行目:その理由(なぜそれが問題なのか)
- 3行目:生活への影響(自分たちにどう関係するか)
- 4行目:自分の主張(この問題についてどう思うか)
- 5行目:なぜそう思うか(自分の主張の根拠)
具体的な練習例
例として、「地方の医師不足」に関するニュースで練習してみましょう:
元記事(要約): 「厚生労働省の調査によると、地方の医師数は都市部の半分以下で、特に産婦人科・小児科の不足が深刻。住民が適切な医療を受けられない状況が続いている。」
5行まとめ
- 記事の主張:地方では深刻な医師不足により住民が十分な医療を受けられない
- その理由:都市部に医師が集中し地方への配置が進んでいないため
- 生活への影響:緊急時の治療や妊娠・出産に不安を抱える住民が増加する
- 自分の主張:医師の地方勤務を促進する制度改革が急務である
- 根拠:医療格差は生命に関わる問題で放置できないから
この5行まとめが、実は小論文の構成と完全に対応しています:
- 1-3行目:問題提起と現状分析(導入に相当)
- 4-5行目:自分の主張と根拠(展開・まとめに相当)
訓練の効果とコツ
この訓練を継続することで、以下の能力が向上します。
- 論点の整理力:複雑な問題を要素分解して整理する力
- 論理的思考力:原因と結果、問題と解決策の関係を考える力
- 簡潔な表現力:限られた文字数で要点を伝える力
- 主体的思考力:受動的に情報を受け取るのではなく、自分なりの意見を形成する力
効果的な訓練のコツ:
- 毎日継続する:1日1記事、5分程度で構いません
- 分野を変える:医療、教育、環境、技術など様々な分野の記事を扱う
- 時事性を重視する:できるだけ新しいニュースを使う
- 添削を受ける:可能であれば先生や友人に見てもらう
発展的な練習方法
5行まとめに慣れてきたら、以下の発展的な練習にも取り組んでみましょう:
10行まとめ:各要素を2行ずつに拡張 反対意見の追加:6行目に反対意見、7行目にその反駁を追加 具体例の強化:体験談や事例を織り込む練習 複数記事の比較:同じテーマの異なる記事を比較分析
実際の小論文への応用
5行まとめで身につけた構成感覚を、実際の小論文に応用する方法
5行→段落の対応
- 1-3行目 → 導入段落
- 4行目 → 展開段落の主旨
- 5行目 → 展開段落の根拠
文字数の拡張
- 各行20-30字 → 各段落100-200字
- 5行計100-150字 → 小論文600-700字
この訓練を続けることで、どんなテーマでも迷わず構成を組み立てられるようになります。
6. まとめ
見解論述の基礎となる小論文構成について学んできました。重要なポイントを改めて整理しましょう。
基本構成の3部構成
- 導入(15-20%):問題提起・テーマ提示・主張の明示
- 展開・論拠(60-70%):複数段落での論証・具体的根拠・反対意見への反駁
- まとめ(10-15%):主張の再確認・未来への提案・個人的決意
成功のためのキーポイント
- 立場の明示:「私は○○だと考える」で構成をブレさせない
- 段落分け:一つの段落に一つの論点で読みやすく
- 具体的根拠:体験・事例・データで説得力を高める
- 論理的一貫性:導入→展開→まとめの一貫した流れを維持
日常訓練の重要性
5行まとめ訓練を継続することで、構成力・論理的思考力・表現力が総合的に向上します。毎日少しずつでも続けることが、確実な実力アップにつながります。
小論文は「型」を身につければ必ず上達する科目です。今回学んだ構成を意識して、まずは5行まとめから始めてみてください。そして徐々に本格的な小論文練習へと発展させていきましょう。
次のコンテンツでは、学部別の時事ネタや主張の作り方について学んでいきます。今回の構成力を土台として、より内容の充実した小論文が書けるよう、さらにスキルアップを図っていきましょう。