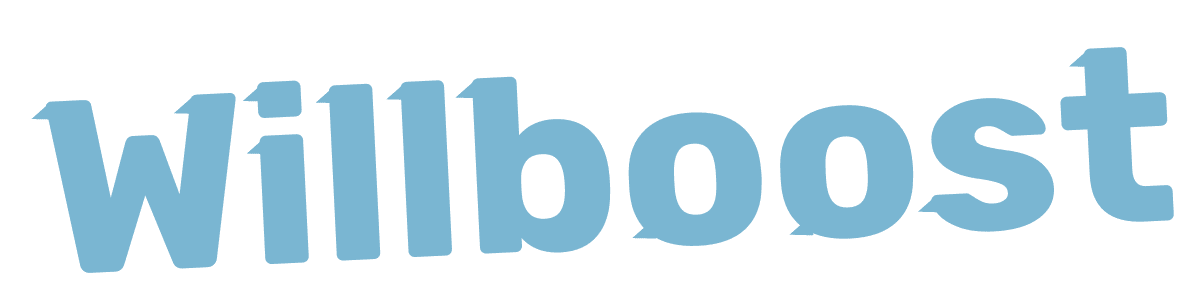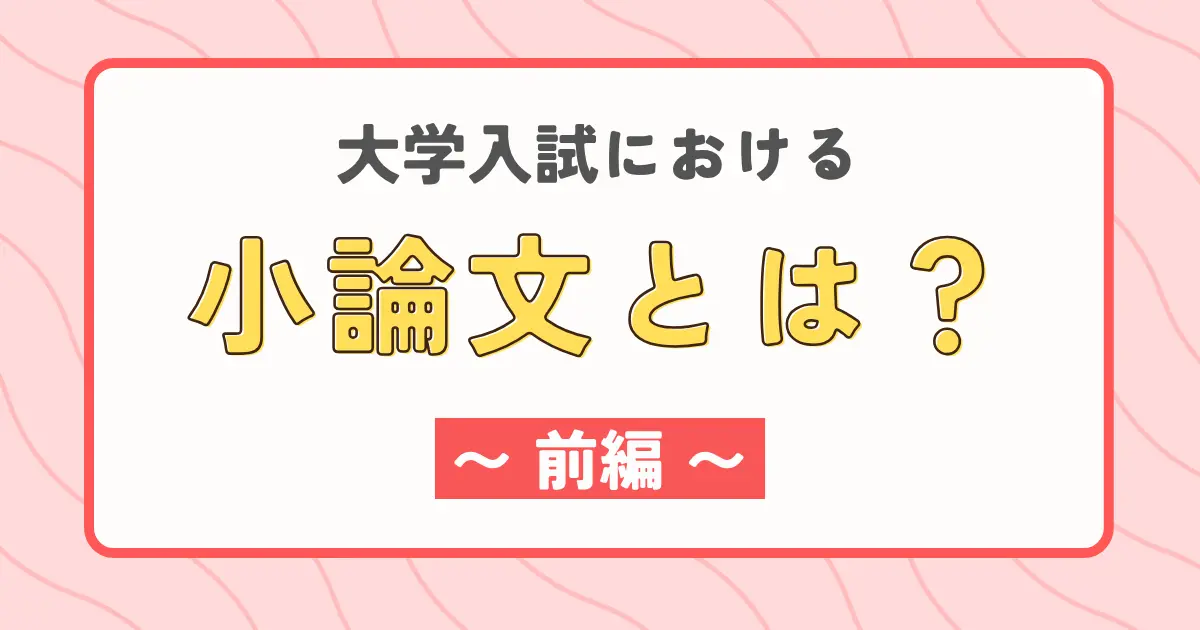「小論文」という言葉を聞くと、どんなイメージが浮かびますか?
「なんだか難しそう」「作文とは違うの?」「どうやって対策すればいいかわからない」
そんな風に思っている人も多いのではないでしょうか。
実は、小論文は医学部入試において非常に重要な位置を占めている試験科目なんです。しかも、単なる「文章を書く試験」ではありません。大学が皆さんの「人間性」や「将来の医師としての素質」を見極めるための、とても意味深い試験なんです。

このコンテンツでは、なぜ大学入試で小論文が実施されるのか、そして小論文を通して大学が何を見ようとしているのかについて、わかりやすく解説していきます。
また、入試方式によって小論文の重要度が変わることも、意外と知られていない事実です。自分の受験戦略を立てる上で、この違いを理解しておくことは非常に大切です。
小論文の意義
なぜ小論文を行っているのか?
大学入試といえば、数学や英語、理科といった学力試験がメインというイメージがありますよね。それなのに、なぜわざわざ小論文という試験を実施するのでしょうか?
答えは明確です。学力試験だけでは測ることができない、非認知能力を評価するためなんです。
「非認知能力」って聞いたことありますか?これは、テストの点数では測れない能力のこと。具体的には、考える力、問題解決能力、コミュニケーション能力、創造性などを指します。
医学部を例に考えてみましょう。将来医師になる人に求められるのは、単に知識を暗記する能力だけでしょうか?
患者さんの話を聞いて症状を理解し、様々な可能性を考えながら診断を下し、患者さんやご家族に分かりやすく説明する。時には難しい判断を迫られることもあるでしょう。
様々な場面で必要になる「考える力」
数学の公式を覚えることも大切ですが、それ以上に「なぜそうなるのか」「他にどんな可能性があるのか」「この問題の本質は何か」といったことを考える力が、医師には不可欠です。
小論文は、そんな「考える力」を直接的に評価できる、数少ない試験方法なんです。
ある医学部の入試担当者は、こんな風に話していました。
「知識は入学後にいくらでも身につけられます。でも、考える姿勢や論理的思考力は、一朝一夕では身につかない。だからこそ、小論文を通じてその基礎があるかどうかを見極めたいんです」
小論文で見られる3つの力について
では、具体的に小論文ではどんな力が評価されるのでしょうか?主に3つの力に分けて考えることができます。
①論理力と思考力
これは、物事を筋道立てて考え、相手に分かりやすく伝える力のこと。医師にとって、これほど重要な能力はありません。
例えば、「AI技術の発達は医療にどのような影響を与えるか」という問題が出されたとします。
論理力のある人は、まずAI技術とは何かを整理し、医療現場での具体的な活用例を挙げ、それによってもたらされるメリットとデメリットを比較検討し、最終的に自分なりの結論を導き出します。
一方、論理力が不足している人は、思いつくままに書き連ねてしまい、何が言いたいのか分からない文章になってしまいがちです。
小論文では、こうした論理的思考力を、実際の文章を通じて評価することができるんです。
②自己理解と主体性
これは、自分自身のことをよく理解し、自分なりの考えや価値観を持っているかということ。
医師という職業は、患者さんの人生に深く関わる仕事です。そんな重要な仕事に就こうとする人が、自分のことをよく知らない、自分なりの考えを持っていないというのでは困りますよね。
小論文では、「あなたが医師を目指す理由」「理想の医師像」といったテーマがよく出題されます。こうした問題を通じて、受験生が自分自身と真剣に向き合い、将来への明確なビジョンを持っているかを評価するんです。
「みんなが医師を目指すから」「安定しているから」といった表面的な理由ではなく、自分なりの深い動機を持っている人を、大学は求めています。
③社会的視野の広さと問題意識の深さ
医師は、個々の患者さんを診るだけでなく、地域の健康問題や社会全体の医療課題にも向き合う必要があります。そのためには、社会に対する幅広い関心と深い問題意識が欠かせません。
例えば、「高齢化社会における医療の課題」「地域医療の現状と改善策」「医療格差の問題」といったテーマが小論文で出題されることがあります。
こうした問題に対して、単に知識を羅列するのではなく、自分なりの問題意識を持ち、具体的な解決策を提案できるかどうか。それが評価のポイントになります。
ある受験生は、自分の祖父が住む過疎地域での医療体験を踏まえて、地域医療の課題について深く考察した小論文を書きました。実体験に基づいた問題意識の深さが評価され、見事合格を勝ち取ったそうです。
小論文と作文・感想文の違いを理解しよう
ここで、多くの高校生が混乱しがちな「小論文と作文の違い」について、しっかりと整理しておきましょう。
作文や感想文は、自分の体験や感じたことを素直に表現する文章です。「楽しかった」「悲しかった」「感動した」といった感情を中心に書くのが特徴です。
一方、小論文は、ある問題に対して論理的に考察し、自分なりの結論を導き出す文章です。感情ではなく、理由と根拠に基づいて主張を組み立てることが求められます。
具体例で比較してみましょう。
作文の例:
「私は将来医師になりたいと思っています。なぜなら、祖母が病気で苦しんでいる姿を見て、とてもかわいそうだと思ったからです。医師になって多くの人を助けたいです。」
小論文の例:
「私が医師を志望する理由は、地域医療の充実に貢献したいからである。現在、地方では医師不足が深刻化しており、適切な医療を受けられない患者が増加している。この問題を解決するためには、地域に根ざした医療活動を行う医師の存在が不可欠である。私は将来、地方の医療機関で働き、予防医学の普及と在宅医療の充実を図ることで、地域住民の健康維持に貢献したい。」
この違い、分かりますか?作文は「かわいそうだと思った」という感情が中心ですが、小論文は「地域医療の問題」という社会的課題を論理的に分析し、自分なりの解決策を提示しています。
小論文では、「なぜそう思うのか」の理由を明確に示すことが最も重要なんです。
医学部入試における小論文の特殊性
小論文は他の学部でも実施されることがありますが、医学部の小論文には特別な意味があります。
なぜ医学部で特に重視されるのか
医師は「人の命を預かる職業」です。そのため、単に頭が良いだけでは不十分。患者さんやその家族と向き合う人間性、倫理観、責任感が求められます。
また、医療技術の進歩は目覚ましく、常に新しい知識を学び続ける必要があります。そのためには、自分で考え、学び続ける姿勢が不可欠です。
小論文は、こうした「医師としての適性」を総合的に評価できる試験なのです。
医学部特有の出題傾向
医学部の小論文では、以下のようなテーマがよく出題されます:
- 医療倫理に関する問題(インフォームドコンセント、安楽死など)
- 社会の医療問題(高齢化、医師不足、医療格差など)
- 医師に求められる資質(コミュニケーション能力、責任感など)
- 科学技術と医療(AI、再生医療、遺伝子治療など)
これらのテーマは、将来医師として直面する可能性の高い問題ばかりです。大学は、受験生がこうした問題にどのように向き合い、考えるかを見ているのです。



このコンテンツは一旦ここまでです。
次は、後編で「大学入試において小論文にどこまでウエイトを置けばよいのか」という点を中心に見ていきましょう。